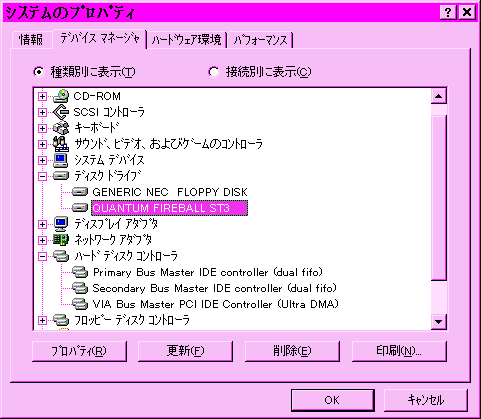
バスマスター
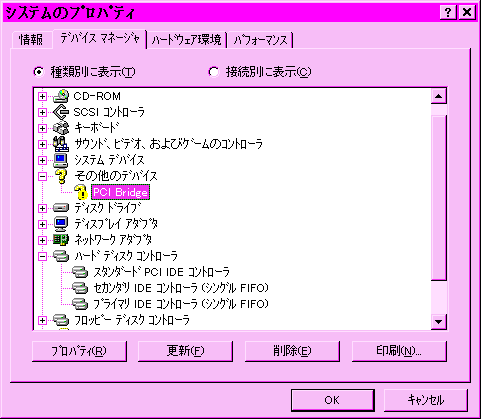
とにかく「シングルFIFO」というのは明らかにPIOモードの状態だ。因みにこの時点でのHDBENCHの値は約7MB/sec強。前のマザーボードの時と同じである。やはり添付のCD-ROM内に「Bus Master IDE Controler」があったのでインストールしてみる。しかし何も変わらない。デバイスマネージャの記述も、ベンチマークテスト結果も。いったいこのCD-ROMはなんなのだ。AOpenの全マザーボード共通なのかな?
やはりAOchip.exeのあったページに「VIA Bus Master (Ultra DMA) PCI IDE Driver for Windows95/NT」というのがあったのでダウンロードしてくる。如何にもそれといった名称である。早速インストールしてみる。ふんふん確かにデバイスマネージャの記述は変わり、まさしくUltra-DMAになったという感じだ。
[デバイスマネージャ(VIA Bus Master Driveインストール後のハードディスクコントローラ)]
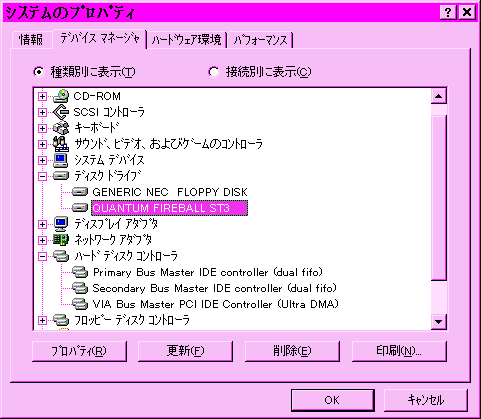
しかも「ディスクドライブ」の方にある「QUANTUM FIREBALL ST3」に驚いた。IDEのハードディスクでこんなの見るの始めて。まるでSCSIハードディスクのようだ。いつもここはIDEのハードディスクだと何を接続しても「GENERIC IDE DISK TYPExx」にしかならなかったのに。これは良さそうだと期待が高まる。さっそくベンチテスト。ところがところが何と4MB/sec弱というひどい結果だ。何度か試みたし、HDBENCHにある「バスマスター」をチェックしてもみたが変わらない。試しに他のディスクベンチも行ってみたがほぼ同じ結果だ。
「ディスクドライブ」の「QUANTUM FIREBALL ST3」のプロパティを見てみると次のようになっていた。
[ハードディスクのプロパティ1]
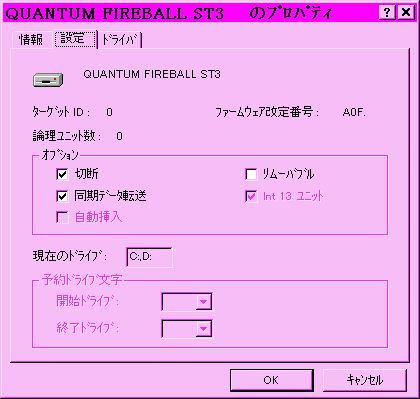
どうも普通のIDEハードディスクのプロパティと違う。バスマスターのはずなのに「DMA」のチェックボタンもないし、SCSIハードディスクのように「切断」や「同期データ転送」にもチェックがついている。
これは後で分かったことだが、やはりこの状態はIDEのハードディスクとしてはおかしいそうである。デバイス名としては、「GENERIC IDE DISK TYPExx」と出るのが正常で、プロパティも「切断」や「同期データ転送」はチェックはおろか、そもそも設定できない(グレーアウトされている)のが正常らしい。
実はPentium-II自作機の時も似たようなことがあった。このハードディスク(Quantum Fireball ST 3.2A)は昨年のPentium-II自作時にはこのマシンに接続していたのだが、この時ASUSのP2L97添付のCD-ROMから440LX用のドライバをインストールしたら、デバイスマネージャの記述は上記とほぼ同じ(勿論VIAの部分はIntel云々だけど)ものになり、テスト値はガクンと下がってしまった。ただこの時はハードディスクのプロパティの方は見なかったのでチェック項目がどうなっていたかは分からない。ただ「GENERIC...」だったような気がする。もしそうでないなら気づいていたはずだから。
テスト値のひどい落ち込みに慌てて、この時はすかさず削除した。しかしなぜか削除しきれず、下記のようになったのである。
[デバイスマネージャ(P2L97の場合)]

結局「Intel 82371AB PCI Bus Master IDE Controllers」というの残ってしまい、その下の子デバイスが日本語になった。ところがこのようなかったら、ベンチマークテスト結果が格段に良くなったのである。詳細にテストしても確実にドライブの性能を引き出し、Ultra-ATAで転送されていることを裏付ける結果なっていた。理由は良く分からなかったが結果オーライでよしとしていた。現在もそのままである。
そこで今回も試みにハードディスクコントローラを削除してみた。結果次のようになった。
[デバイスマネージャ(VIA Bus Master Driverの削除後)]
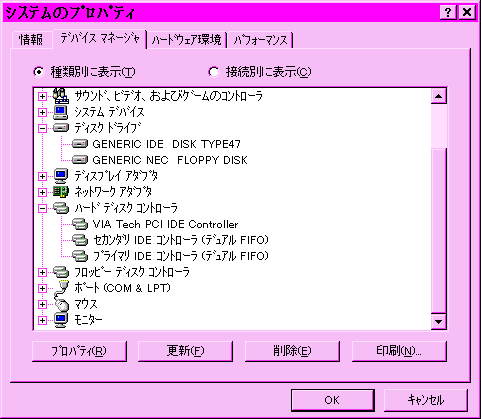
P2L97の時と完全に同じではない。子デバイスはやはり日本語になったが、親デバイスはちゃんと変わってしまった。恐る恐るベンチテストを試みると、これが大変いいではないか。9MB/sec弱出ている。P2L97につなげていた時と同じパフォーマンスになった。ハードディスクのプロパティも次のようになった。
[ハードディスクのプロパティ2]
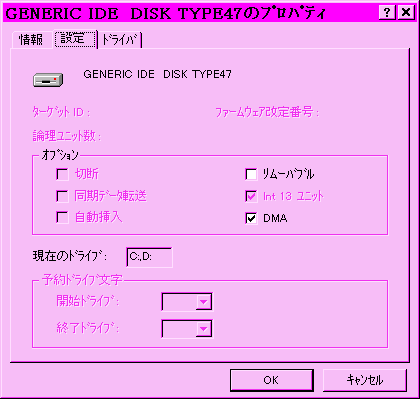
よしよし「切断」と「同期データ転送」もグレーアウトになったし、ちゃんと「DMA」のチェックボタンもある。正しいIDEハードディスクのプロパティになったようだ。
ただし速度的にP2L97の時と同じになったのはドライブそのものの性能が出るシーケンシャルで比較的大量のデータ転送の場合だけである。バッファー(キャッシュ)の読み書きなどは純粋な転送速度に近いものがでるはず(P2L97の時は30MB/secくらい出ていた)なのに、それほど速くなってない。「バスマスタ(DMA)」にはなっているものの、所謂「Ultra-DMA」にはなっていないように思えた。
そこでちょっと面白いものを入手した。マスタードシードのページに「トラブルの多いVIAのバスマスタードライバの代わりに、Windows標準のバスマスタードライバを使うためのパッチ」というのがあった。パッチとはいっても、何か仮想デバイスを書き換えるとかいうバイナリデータではなく、レジストリを変更するだけのようであった。EPoXマザーのユーザが作ったものであると書いてあったが、infファイルを見てみると、MVP3ならどんなマザーボードでも使えそうな記述だったので、とりあえずこのパッチを当ててみることにした。当てた後は次のようになった。
[デバイスマネージャ(標準バスマスターバッチをあてた後のハードディスクコントローラ)]
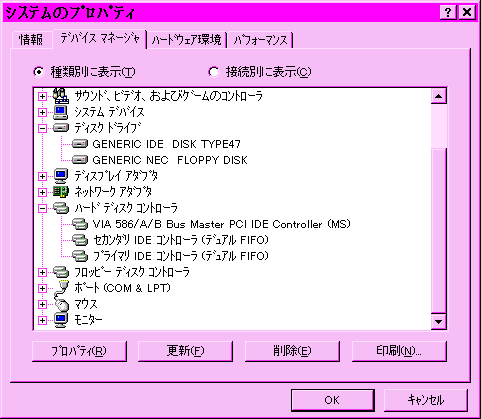
見た目は良さそうなのだが、やはり「Ultra-DMA」で転送されているような結果にはならなかったし、シーケンシャル速度も速くも遅くもならなかった。どうも「Windows標準のバスマスタードライバ」とは単なるバスマスター転送を可能にするだけで、「Ultra-DMA」をサポートしている訳ではないのかもしれない。とにかくUltra-DMA転送に関しては、VIAがきちんとした「Ultra-DMA用のバスマスタードライバ」を作ってくれないことには実現しそうにもない。
まあDMA mode2にはなっているようだし、現実にはこれで殆ど問題ないはずなので、VIAに期待しつつ、今回のところは「IDEコントローラ」に関してはこれにて一件落着と行きたい。ところで最初のVIAのコントローラを削除した後のものと、パッチを当てたものは、性能は全く変わらないのでどちらでもいいと思う。一応曲がりなりにも「Bus Master」という記述のある後者の方が気分的にいいので、私はパッチを当てた方でいくことにした。しかしこのパッチを当てると「システムデバイス」の記述も以下のように変わった。
[デバイスマネージャ(標準バスマスターバッチを当てた後のシステムデバイス)]
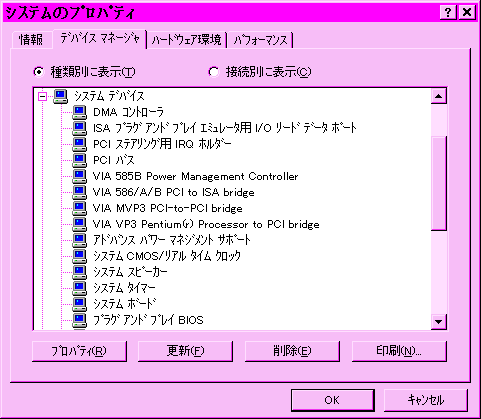
語句が若干違うが、内容的は同じものだろう。ただし「AGP」という単語が無くなったので、AGPを使いたい人で気になるようなら、VIAの方にしておいた方がいいかもしれない。